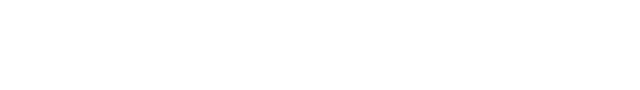ニセ医学に騙されない方法
YoutubeやSNSの発展により、誰でも簡単に情報発信できる時代になりました。スマホを開けばすぐに情報収集できる反面、とんでもねえデマやニセ医学がさも正しき情報かのように出回り、コロッと騙されてしまうリスクが跳ね上がっています。
最近だと、子宮頸がんワクチンにはじまり、コロナワクチン、マスク論争、自然派、サプリ、発達障害とかがよく狙われます。
今回は、そういう間違った情報に騙されないコツについて書いてみたいと思います。
わかる人にはわかる
10年間それなりにまじめに医療に取り組んで来た身としては、ニセ医学とか間違った情報は割とすぐにわかります。なぜかというと、医者っていうのはそもそもニセではない本物の医学についても、常に疑ってかかるクセがついているからだと思います。医者の仕事の一つは、いまやっていることに「それって本当?」と問い続けることといっても過言ではありません。
世界中で行われている研究により、現代の医学知識は2か月ちょっとで2倍になるといわれているくらい、常に膨張し続けています。今正しいと信じられている情報も、あっという間に塗り替えられてしまうことがしばしばあります。それに必死でくらいついていくためには「これが正解」とか言ってあぐらをかくわけにはいかず、いつでも「自分の正解を自分で壊す」必要があります。
人を動かすのは心
ところで、私たちの行動にもっとも影響をあたえるのはどういう情報でしょうか。
思うに、人の行動をもっとも変えるものは、衝撃的な体験だったり、尊敬する先輩の言葉だったり、他人の生き様だったり、大事な人を守りたいという気持ちだったり、心に強く訴えかけるものではないでしょうか。
自分自身を振り返っても、人生の転機となるようなできごとは、言語化すれば取るに足らないけれど、当時の自分にとっては、心が大きく揺れ動くような出来事だったと思います。
「心」とはしばしば合理性だとか科学とはかけ離れたところにあります。
「るろうに剣心 3巻」で恵を助けに行くのを渋った左之助を剣心が諭す名シーンでたとえてみましょう。
ここでの剣心のセリフ
「いつも気丈にふるまっているが時にほんの一瞬拙者たちを寂しそうな瞳でみていたでござる。心を許せる家族に等しい仲間を探している、捨てられた子犬のような瞳でござる。人が動くにいちいちワケが必要ならば拙者のワケはそれで十分でござる」
これは、剣心の生き様を象徴する言葉であり、左之助はそこに強く胸を打たれたからこそ、親友の仇ともいえる恵を助けるために一歩踏み出すわけです。
この名セリフが
「助けに行った場合に考えられるリスクは〇〇で、ベネフィット(利益)は〇〇でしょ? それらを天秤にかけてみると、助けに行く方がトータルで見てベネフィットが勝るから合理的だと思うよ。拙者のワケはそれで十分でござる」
だと台無しなワケです。なんの共感も得られません。
エビデンスとは
しかしながら、現実のエビデンスというのは、リスクとかベネフィットとかを誰がどんなテンションで言っても同じになるように定量的に評価したものです。それは何のドラマ性もなく、淡々とした一見つまらないものだったりします。
エビデンスについて、真面目に突き詰めていくと、実はほとんどすべてのものが「あやふや」という結論に到達します。この薬は効くかもしれないし、効かないかもしれない。副作用はあるかもしれないし、ないかもしれない。重症化するかもしれないし、自然に治るかもしれない。ワクチン接種すれば感染しないかもしれないし、するかもしれない。そんなんばっかです。「絶対これがオススメ! メリットしかありません」みたいなわかりやすい推奨はたとえガイドラインであってもあり得ないのです。
SNSは運営する側からすれば、つかみや印象が重要だから、とにかく興味をひくように、わかりやすく、シンプルに(断言し)、さらに言えば不安をあおるように訴えかけてきます。
エビデンスは日本語で言えば「証拠」ですが、その言葉の意味ほどには物事を断定するものではありません。そういった「あやふや」なエビデンスをいかに使いこなして、患者さんのニーズと結び付け、個人個人にとっての最善を探していくか。それを専門として日々勉強しているのが我々医師というわけです。
そんなわけで、注意が必要な典型的パターンはコチラとなります。
①「みんなやってる」
②「〇〇教授が推奨」
③「〇〇だとやばいかも」「〇〇やればOK」
④「〇〇であることがこの論文で示されています」
⑤「〇〇したら病気になった。〇〇ってやばい」「〇〇したら病気が治った。〇〇ってすごい」
⑥「やつらが金儲けのためにやってること」
次回はこれらについて解説していきたいと思います。