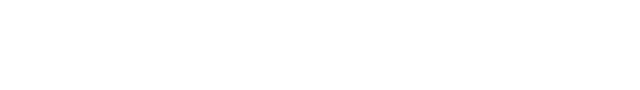実践! SNSの疑似科学に騙されないコツ!
前回の記事で「心を揺さぶる医療情報はうさん臭い」という話をしました。
裏を返せば、ネットにはびこるニセ情報に惑わされないためのポイントは「情報から心を揺さぶる要素を排除する」ということになります。
というわけで今回は実践編です!
心を動かされやすい情報への対処法を見ていきましょう。
①「みんなやってる」
人は連続して同じ意見を聞くと、それが正しいような錯覚に陥るものです。ある心理学の実験では、普通にやると正答率100%の簡単な問題でも、目の前で何人ものサクラが同じように間違いの選択肢を選んだのを見た後で質問されると、正答率が60%くらいに下がるそうです。それが、健康や医療など簡単には検証できない内容ならなおさらです。「赤ちゃんはみんな15時間以上眠るものです」とか「医師の多くは母乳だけでなく少量のミルクを足すことを推奨しています」とか言われると、惑わされます。
でも「みんな」とか「多くの」とかは誇張するための常套手段で、言ってる本人にもその規模がどれくらいかちゃんとわかっていない場合があります。
こういう言葉が出てきたら「私が知っている一人か二人」に置き換えてみましょう。「赤ちゃんは私が知っている一人か二人は15時間以上眠ります」「私が知っている医師の一人か二人はミルクを足すことを推奨しています」
ふうん、くらいで聞き流せますよね。それでOKです。もともとそれくらいの信ぴょう性ということです。
②「〇〇教授が推奨」
言ってる内容ではなく、言っている「人」を強調するパターン。〇〇が言ってる! という言い回しはとりあえず興味を持ってもらうための「ヒキ」のテクニックですが、大事なのは当然その内容です。内容が妥当であれば言っているのが教授だろうがその辺のおじさんだろうが価値は同じです。でも「その辺のおじさんが推奨している糖尿病予防法!」とか言うと内容が素晴らしくてもそもそも手に取ってもらえない確率が高いので、「〇〇教授が推奨する糖尿病予防法!」というヒキでとりあえず手に取ってもらえるようにするわけです。(僕自身もYoutubeでは「小児科医が解説します」とか言ってます)ただ困ったことに、内容がめちゃくちゃなのに、ヒキだけがっつり教授とか場合によっては医療者ですらないインフルエンサーを使ってくることがあるため、注意が必要です。
対処法はもちろん、「〇〇教授」を「その辺のおじさん」に変えてみましょう。「うちのパパ」でもいいです。「うちのパパが言ってる糖尿病予防法!」、、、。それでも納得いく内容であれば、間違いないと思います。
③「〇〇だとやばいかも」「〇〇さえやれば安心」
不安をあおって、希望を差し出すテクニックです。真剣に悩んでいる人ほど騙されます。バタフライ式ハイハイとかね。
医療には必ずいい面と悪い面が混在しますので、何か一つのことで「やばくなる」とか「安心」とかいうことはあり得ません。この言い回しをしている情報はまず間違いなくフェイクか誇張です。「〇〇が発達に悪影響」とか「〇〇をすれば風邪をひかない」とか。
対処法は、断言している情報を見つけたら最後に「~という側面もあるかもしれないね」をつけてみましょう。「〇〇が発達に悪影響という側面もあるかもしれないね」「〇〇をすれば風邪をひかないという側面もあるかもしれないね」
④「〇〇であることがこの論文で示されています」
世の中には科学論文は山ほどあります。ある薬が効くと言っている論文と効かないと言っている論文が混在することもザラです。だから自分の主張したいことを支持するような論文を探すのは割と簡単です。問題はその論文で言っていることが本当に科学的に妥当なのか? 万人に当てはまるのか? 反対のことを言っている論文はないのか? ということをきちんと吟味したうえで引用しているかどうかです。そのあたりを吟味せず、自分に都合の良いそれっぽい文献だけを引用することを「チェリーピッキング」といいます。引用文献があることで自説の説得力を増やすためのテクニックです。
対処法は、引用文献を自分で読んで吟味することです。ただこれは慣れていないと難しいと思うので、引用している人の能力と誠実さを信じるほかありません。なお医療者以外が提示している引用文献はたいていちゃんと読むと違うことが書いてあるので、基本的に無視でいいと思います。
⑤「〇〇したら病気になった。〇〇ってやばい」「〇〇したら病気が治った。〇〇ってすごい」
ワクチン関連でよく使われる論法です。ワクチンを打った翌日に死亡した。だからこのワクチンは死ぬ可能性があるワクチンだ。という感じのやつです。
有名なたとえで、「ほぼすべての人が、死亡する24時間前に水分を摂っている」だから「水分摂取は死亡の要因になっている」というのがあります。これが間違いであることは誰でも簡単にわかります。しかし「水分」が「ワクチン」に置き換わると、途端に信じてしまう。不思議な錯覚です。
対処法は、「Aの次にBが起きる」ことと「AがBを引き起こしている」ことは全然別物だという認識を持つことです。
⑥「やつらが金儲けのためにやってること」
陰謀論とかでよく出てくるやつですね。風邪薬は製薬会社が設けるための陰謀とか、コロナワクチンは医者が設けるための陰謀とか。これについては、まあ半分は合ってて、お金を儲けるためにやっているのは間違いないですよね。ただこれって、「八百屋さんが野菜を売っているのは金儲けのためだ」「うちの父が毎日会社で働いているのは金儲けのためだ」というのと同じで、生計を立てるために働いているのは間違いないし、できればたくさんのお金を稼ぎたいから頑張っているわけです。でもそのことと、売っている野菜の品質や会社の社会貢献度とは関係ないわけです。もちろん劣悪な商品やサービスで不当に儲けを得ようとする輩もいるとは思いますが、「お金が儲かる」=「金儲けのこと以外はどうでもいい」というのはさすがに言いがかりが過ぎると思います。ほとんどの医療者はお金がもらえれば患者のことなどどうでもいいなんて思っていなくて、日々より良い医療を追求していて、その対価としてお金をもらいたいと思っていると思います。
対処法は、とりあえずお金のことは置いておいて、本当にその医療が科学的に妥当なのかどうかで考えればいいと思います。
他にも、Before&Afterを信じるなとか、経験者の感想は自分に当てはめてはならないとか、根拠なき断言はだいたい嘘とか、いろいろポイントはありますが、今回はこのへんで。
SNSの大流行に伴い、有象無象のなんちゃって医学情報にイライラした一小児科医のたわごとにお付き合いいただきありがとうございました。皆様ネット情報で不安になった際はぜひ一度外来でご相談ください。