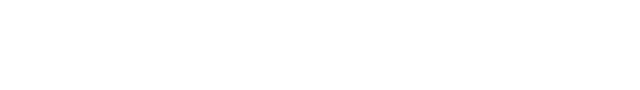周産期新生児学会に行ってきました
連休を利用して、大阪で行われた周産期新生児学会に参加してきました。
学会参加は5年ぶり。コロナでWEB開催が進化して現地に行かずとも主要な講演が視聴できるようになったのもあるけど、NICU勤務じゃなくなって自分から発表することがなくなったというのが大きいです。
こどもの頃は学会っていうと、なんか偉い人たちの集まりというくらいでそこで何が行われているのかまったく知りませんでした。(なぜか学会会場というと、悪い奴らに襲撃されがち、というイメージがありました。なぜだろう? そういう漫画とかあったかな?)
このブログを読んでくれている方も、学会には縁遠い方が多いと思いますので、どんな感じなのかを簡単に説明します。
学会では大きな会議場(今回だと大阪国際会議場)を借り切って、いくつかの会場で同時進行的にいろいろな発表が行われます。参加者は各々好きなように会場を巡り、聴きたい講演を聴きます。イメージ的にはロックフェスみたいな感じだと思います。(フェス行ったことないけど)
何百人も入る大きいホールでは高名な先生の招待講演やテーマを決めて議論するシンポジウムなどが開かれます。小さな会議室では僕の様ないち医師が10分くらいずつ演題を発表します。スライドを使ってプレゼンするので口演と言います。それらとは別にワンフロア使った大広間があって、そこではポスター発表といって、こんな感じのポスターをB紙くらいのサイズに印刷したものがたくさん貼ってあります。
ポスター発表のスペースは大広間の半分くらいで、残り半分は企業が最新の医療危機を置いて、プロモーションをしています。保育器とかもどんどん進化していてスゴイです。
そして、通路の一角に、書籍スペースがあります。これが意外と楽しいスペースでして、医学書ってわりと大きな本屋さんに行かないと置いてないし、まして周産期関連の本はちょろっとあるくらいなので、周産期の本ばっかりこんなにもまとまって置いてあるのはレアなのです。全部ほしくなる笑
あと、学会では、偉い先生方が集まって、今後の学会の在り方や日本全体の周産期医療の方向性などの話し合いが行われています。たぶん。これは自分がそこまで偉くなったことがないので想像ですが、何やら理事の先生などが集まって何かをしているのは確かです。そして夜にはなかなか会えない遠方の人たちと飲み会などが行われます。情報交換大事です。
僕がはじめて学会に参加したのは大学生の頃でした。その時は福岡で開催された小児科学会だったのですが、その頃はぎりぎりまだ製薬会社からの豪華なお弁当とか接待とかがまかり通っていた時代だったこともあって、企業ブースでは無料でクレープを配っていたりして、お金のない学生の自分は「なんてスゲー祭だ! 学会サイコー!!」と歓喜したものでした。(不純)
さすがに今はそういうのはないですが、自分の興味ある分野の話を一日中聞けるのは幸せな時間です。
今回の学会で印象に残ったのは、ダウン症候群のある子の小学校以降のライフコースの話と、新生児殺人の話でした。
ダウン症のある子って、現在は平均寿命60歳と言われていますが、ほんの50年前までは、平均寿命2歳! だったそうです。だから、成人期以降のライフコースはいまいち知られていなかった。だから内科の先生も小児科の医師もよくわからず、ほったらかされがちなんだそうです。
確かに、自分が新生児科医として診たのは、生まれたときの合併症の検索や管理だとか、就学するくらいまでのフォローで、経過が良好だとそこらへんで手を離れてしまいがちなので、その後どうなるのかまではあまり知りませんでした。そうこうしているうちに成人してしまうと、小児科領域ではなくなってしまう。
自分の今の外来でも、ダウン症候群のある子は何人かいますので、大変勉強になりました。
そして、よくニュースなどであがる新生児の殺人、遺棄の話題。その母親たちの心理の話もとても勉強になりました。多くのお母さんは、もともとの認知機能の未熟性に加えて、家族から孤立したり、迫害されたりという背景を持っているそうです。未然に防ぐためには、そうした母たちがまだこどものうちの介入がとても大切だと思いますし、それは小児科クリニックにも十分関係することだと思いました。
どちらの話題も、こどもと家族の人生そのものを大切にし、踏み込んで関わっていくという、第一線で活躍する先生方の熱量を感じました。自分が掲げていた理念の重要性を再確認するきっかけにもなりました。
大阪までの2時間半はなかなか大変ですが、やはり現地での学会参加は臨場感もあってよいですね。
タイミングが合えば、また来年も参加したいです。