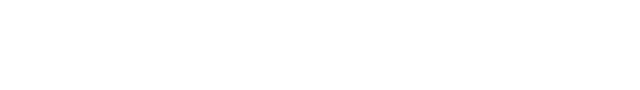おたふくかぜワクチンはなぜ定期接種にならないか
乳幼児ワクチンの中でいまだに定期接種化されないおたふくかぜワクチン。一個だけ有料なもんだから悪目立ちして、「任意ってことはやらなくてもいいんでしょ?」とスルーされがちな不憫なワクチンです。
諸外国では麻疹風疹(MR)ワクチンと合わせてMMRワクチンとして接種することが多いですが、日本ではMMRワクチンが使えないので、MRワクチンとおたふくかぜワクチンを別々に接種するというのが現状です。
ところで前回の記事でMMRワクチンが自閉スペクトラム症のリスクになるという不正論文についてご紹介しました。
日本でMMRワクチンがないのはこの騒動のせい?! と思いたくなってしまいますが実はそうではありません。
一体なぜ中止されてしまったのでしょうか?
自閉症騒動の前から禁止されていたMMRワクチン
日本でMMRワクチンが使われていたのは1989年から1993年までのわずか4年間でした。件の論文が発表されたのが1998年なので、自閉症の話題が出る以前から日本ではMMRは使用中止になっていました。
中止になった理由は「自閉症」ではなく、無菌性髄膜炎という副反応でした。
当時日本で使われていたおたふくかぜワクチン株は諸外国のものとは別の株だったのですが、諸外国に比べかなりの高頻度で無菌性髄膜炎を発症したために、健康被害が大きいとの判断で中止されたのでした。
しかし政府としては、麻疹風疹撲滅運動にブレーキをかけたくなかったため、以降はおたふくかぜを切り離し麻疹風疹(MR)ワクチンとして定期接種化にこぎつけました。
さてその切り離されたおたふくかぜワクチン。「え、副反応やばいんじゃん!接種して大丈夫?!」と不安になるのは当然のことです。
現在使われているおたふくかぜワクチンのリスク
おたふくかぜワクチンも当時のまま何も変わらないということはなく、現在使われている株では以前のものと比べて格段に安全になりました。しかしそれでもやはり一定の率で無菌性髄膜炎は起きてしまいます。
それなのになぜ推奨されているかというと、そもそもおたふくかぜという病気が無菌性髄膜炎を発症するものだからです。
おたふくかぜにかかって無菌性髄膜炎になるか、ワクチン接種して無菌性髄膜炎になるか、そのリスクを冷静に比べることが大切です。
おたふくかぜに自然感染した場合
• 1,000人に約10〜100人が無菌性髄膜炎に
• さらに重い合併症(難聴や精巣炎)もあり
ワクチンを接種した場合
• 10万人に数人程度が無菌性髄膜炎に
• 重症化はまれ
このように、感染してしまう方が圧倒的にリスクが高いのです。ワクチンは完璧ではないけれど、安全性は大きく改善されています。
なかなか定期接種化されない理由
ワクチンを接種する方がリスクが低い(=接種が望ましい)のであれば、なぜなかなか定期接種化されないのでしょうか?
想像するに、以下のようなことが要因になっているのではないでしょうか。
• 過去の副反応の記憶が強く、行政が慎重になっている
• 定期接種化に必要な大規模調査や費用の問題
• 国のワクチン政策の優先順位(麻しん・風しん排除が先行した経緯)
こうした背景から、専門家が「定期接種化が望ましい」と繰り返し提言しているにもかかわらず、まだ進んでいないのです。
ただ国では現在進行形で定期接種化の議論は進んでおり、安全性に関するスタディも動いているので、遠からず定期接種にはなると思います。
今後定期接種化されたら日本でもMMRワクチンが採用されるかも?
現在、海外では「麻しん・風しん・おたふくかぜ」を一度に予防できるMMRワクチンが主流です。
日本でも第一三共が2024年に製造販売承認申請を出しており、定期接種化と同時にMMRの導入を狙っているものと思われます。
企業戦略はさておき、現場にいる身としては、痛い注射が一本でも減ってくれるのは非常にありがたいので、定期接種化&MMR承認、ぜひともすすめていただきたいですね!